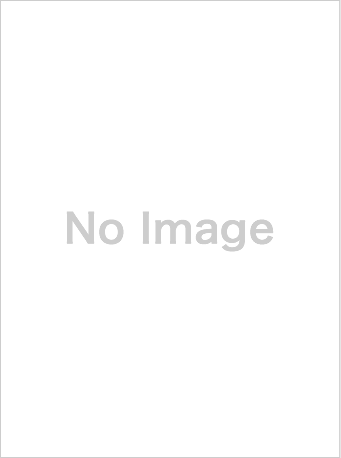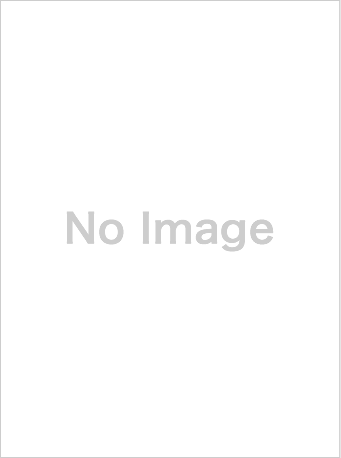11月の読者会は、特集1「『学校×性』のタブーを超えよう」の中から田代美江子さんの「学校でこそ包括的性教育を—足立区の実践をあたりまえに」を読み合いました。
田代さんの報告は、今年3月東京都議会文教委員会で、足立区の中学校で行われていた性教育が「不適切」だと問題視(攻撃)したことに対して、議会が教育内容にかかわって発言することの不当性を指摘するとともに、この中学校の性教育実践の正当性と同時に、その実践のもつ今日的意味と先駆性を「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に示される包括的性教育に依拠しながら、(1)性の権利(2)性に対する肯定的アプローチ(3)「多様性」を前提としてジェンダー平等(4)学習者の生活実態と必要性、という視点から明らかにするとともに、学校の果たすべき役割の重要性ついても指摘している。
話し合いでは、足立区の実践そのものについてもう少し具体的に記述されるとよかったのではないか。いやいや、なかなか具体に触れるのは難しかったのかもしれないなどという感想から始まり、中学、高等の先生からは性をめぐる子どもたちの実態や、性教育の取り組みの現状などが語られた。オーストラリアの日本人学校で教えた体験のある先生からは、日本は「みんな一緒」という意識がどこかにあって異質なものを排除することになりがち。オーストラリアではLGBTの人も、そうでない人も、たとえば職場ごとにパレードに参加したりしていた。多様な性のあり方に対する社会の受け止めが日本とオーストラリアではかなり違うと感じた。ただ、今の学校の条件の中で生徒たちの多様性を前提にいろいろ改善したりやろうとしても、なかなか難しいことも多々ある。混合名簿だけでなく、制服だってそういう視点から見直しされてもいいはずでは。課題はいっぱいある。
田代さんは、LGBTとかセクシュアルマイノリティという言葉をカテゴライズすることで、私たちの間に境界線を引き、それらの人たちを「かわいそうな人たち」と他人事として捉えてほしくない。だから、それらの言葉は基本的に使わないと述べている。言葉として概念化し命名することは社会に対して問題や課題を可視化することであるように思うのだが。そのあたりをどのように考えているのだろう。
足立区の実践を攻撃する都議は、「羞恥心」をもったり「嫌悪感」を感じたりする子どもがいることを理由に「個別指導」で行うべきと、子どもたちがみんなで性について学ぶことの必要性を否定しているようだが、そういう「羞恥心」「嫌悪感」を性や、性を語ることについて感じてしまうこと自体が教育課題であると言えるのではないだろうか。
田代さんの言う「今の子どもたちが置かれている状況、生活実態を踏まえたところから出発する」性教育実践の必要性を感じた。
|