2011年08月29日
かもがわ出版からの「3・11 あの日のこと、あの日からのこと ― 震災体験から宮城の子ども・学校を語る」が動き始めると読者の反応が気になる。Sさんから感想のメールをいただいた。たくさんの語り手の話でまとめあげられたもの。感想を私だけのものにできない。Sさんには無断りだが次に紹介したいと思う。
『3・11 あの日のこと、あの日からのこと』昨晩読みました。
11時過ぎに読み始めたのですが、眠気も飛んで最後のページまで一気に読みました。
この読後感の良さはどこから来るのでしょう。すさまじい中を生きのびた子ども・人々の事実・記録ということ、それぞれの方の確かな表現力、そういうことはもちろんあるのでしょうけれど、私はやはり教育という営みの深さ・大きさに改めて感じ入った気がします。
「私たちは普段から子どもの命を預かっていたんだ」とどなたかが書かれていましたが、それは多分震災のような事でなくてもそうだし、そこで守られるべきその命とは、たんに呼吸をしているという意味の命というだけではなく、あらゆる意味での「いのち」なのだという意味で、やはり教師は ”聖職”なのだと改めて思ったのです。(組合の先生たちはあまりお好きな言葉ではないようですが。)
田中先生のはもちろんですが、ご一緒の臨床教育学会準備チームのお二人の方の文にも深く共感しました。
本の全体構成もいいですね。
ひとつだけ言うとすれば、表紙と帯に「教師」と言う言葉はありません。でも、読むとやはり「教師」は欲しい気もしました。
それと、「震災体験から宮城の子ども・学校を考える」とサブタイトルにあって、帯に「被災地から踏み出す教育再生への一歩」とあるので連続して読むとやや「濃い」感じもしました。教育に関心のある方が手に取るのでしょうから、それでも良いのでしょうけれど。
この本を読んでいただくことでお互いのこれからを考える素材になることができればという願いと同時に、私たち研究センターがこれから何を考えていくべきかの示唆を得たいというねらいもある。率直なご感想をお寄せいただくとうれしい。
2011年08月23日
7月2日の語り合う会終了後、かもがわ出版の編集者Mさんから本にまとめたいという話が出てアッという間にまとまった。しかも8月中に仕上げるというもの。
それからがたいへん。Mさんたちと毎日のように連絡を取り合う。そのたびに、仕事の手順の良さに驚く。電話・メールのたびに日ごと仕事がすすんでいることがわかる。すすみながら細部が修正されていくのもよく見える。
Mさんから送られてきたメールの主なものを拾ってみる。(この間に編集実務担当のWさんからのメール・電話、Mさんからの電話もしょっちゅう。)
24日 校正刷りを作成し送り、28日までにもどしてもらうよう頼んだと連絡。
順調にすすめば8月17日に見本納品予定で刊行可能とのこと。
25日 カバーラフについての意見を・・。
25日 カバー修正案届く。
26日 チラシリード届く。
27日 読者用チラシ修正版、確認を。
27日 ページ数定まり、本体価格決まるとの連絡。
29日 カバーと帯の確認を。
29日 執筆者リストと奥付についての確認を。
1日 本の成り立ちの断り書きの確認を。
2日 カバーに入る説明文の確認を。
2日 オビの確認を。
2日 本文写真撮影者の名前の確認を。
18日 本を送ったとの連絡。
こうして「3・11 あの日のこと、あの日からのこと ― 震災体験から宮城の子ども・学校を語る」ができあがった。
最後にTさんの感想の一部を紹介する。
帰りの新幹線で全部を読み通してみました。デザインもそうでしたが、内容(人々の文章、子どもの文章、そして写真)も、悲しさと美しさと、それでも生きていこうとする静かな意志が同居しているように、あらためて感じました。「3・11」の「記録」としての価値ももっているように思えました。
おかげで、仕事をしたという充足感をもつ。関わらせてもらい、Mさんたちに深く感謝。
2011年08月16日
終戦66年を迎えた昨日について、K新聞の見出しのひとつに「首相と全閣僚靖国参拝せず」とあった。この「せず」がなんとなく気になったのはどうしてか。
45年8月15日については、山の分校の小学4年生だった私にも、何年経っても薄くなることのない記憶がいくつかある。
今年と同じように焼けるような陽ざしで体を動かすたびに汗がしたたりおちてきたたこと、母は唐鍬をかついで松の根掘りに朝から山に出かけ汗まみれになって昼近くに戻ってきたこと、昼にラジオのある隣家に子どもも一緒に集まり“玉音放送”を聴きその内容はほとんど理解できなかったがなんとなく戦争に負けたらしいということを感じたこと(それを知った時の大人の様子はまったく記憶にない)、母たちは午後山には行かなかったこと、道路向かいの豆腐屋の生け垣のムクゲの花の色がすごく目立っていたこと、などである。
 トラック島にいると言われていた父は何日待っても音沙汰なく、突然翌年、霞ヶ浦の病院にいるとの連絡があり、母が迎えに行き、仙台の大学病院で手術、病名はアメーバー赤痢。これは母から聞いたもので、父は病気のことも含めて戦地のことは何一つ言わなかった。しばらく仕事に就けない間、休職教師の父と2人で紙巻きタバコつくりをして闇で売り生活の足しにした。これが唯一の父との思い出と言っていいかもしれない。
トラック島にいると言われていた父は何日待っても音沙汰なく、突然翌年、霞ヶ浦の病院にいるとの連絡があり、母が迎えに行き、仙台の大学病院で手術、病名はアメーバー赤痢。これは母から聞いたもので、父は病気のことも含めて戦地のことは何一つ言わなかった。しばらく仕事に就けない間、休職教師の父と2人で紙巻きタバコつくりをして闇で売り生活の足しにした。これが唯一の父との思い出と言っていいかもしれない。
7・8年前になるが、友人の紹介で、「トラック島日誌」(窪田精)を読んで、父のトラックでの暮らし、病気の原因、帰国は奇跡に近かったことなどが想像できた。
窪田はあとがきの1部で、「トラック島では、約8千名の陸海兵士が死んでいる。そのほとんどが餓死だった。私はトラック島で、生きながら人間の地獄を見た。戦争というものの実態を、まざまざと見た。私はもしも生きて日本に帰ることができたならば、この島でみたものを、なんとかして書き残したい。それが死んでいったものたちにたいしての、生き残った自分の義務である」と書いている。
この本を読むことで私は、何も言わなかった父を少し理解できたように思った。
父の病気は再発。死後どういういきさつか、戦病死ということで靖国に祀られたと連絡があった。母は遺族会の清掃にいそいそと参加したことがあった、1度だけだったが。
誰もが口では否定しながら同じ悲劇を繰り返している「『戦争って』何なんだろう・・」は、私の中に変わりなく居座りつづける最大の問題である。
2011年08月11日
今日で震災から5カ月になる。
被災地で仕事をつづける教師たちを、「あの人は・・」「あの人は・・」とひとり一人を浮かべる。夏休み期間ゆえに、真っ先に思うのはゆっくり休めているだろうかということ。「休めているか」を言いかえれば「自分の時間にできているか」ということ。
日々の暮らしの中でも自分の時間をとれると、それをどんなことに使おうと、翌日が妙にすっきりしてくるものだ。子どもの側に立って言えば、センセイに絶対そうあってほしいと願っているはず・・・。
在職中もそのごもしばらく、毎週1回の夜のサークルに出つづけた。よそ眼にはずいぶんきついように見えるかもしれないが、私には自分でその場にいることを選び参加していたので、何ひとつ苦痛はなかった。私が仕事をつづけられたのはまちがいなくその場に通いつづけたことに会ったと思う。
いつから、どうしてこうも世の中に“教師不信”と思われるいろいろなことがひろがったのだろうか。こういう世の中だから仕方ないのかもしれないが、教育行政や、はては同じ屋根の下で一緒に子どもを育てているはずの管理職まで教師を縛っておかないと済まないと思われる不信感を露わにする方もおるそうな。とても私には考えられないことだ。
被災地を歩いて聞いた、3・11の教師の働きについては頭が下がる話ばかりだった。話を聞くたびに、こんな教師たちのいることを自分のことのように誇らしく思えた。
あっという間に終わってしまう休み、少しでも多く自分の時間にしてほしい、そして引きつづき続くだろうこれからを子どもたちのために力を入れてほしいと願う。
2011年08月06日
知らないうちに8月に入っていた感じだ。
7月2日の「震災を語り合う会」が終わるまではそのことで頭がいっぱいだった。いつもの集会と違って始まるまでその是非が自分の中を行き来しているのだからたまらなかった。集会直後、かもがわ出版から、この集会と震災特集の通信、そして聞き取りをひとつにした緊急出版の話、私は大いに驚いたが、その日のうちに決定。特別なことをしたわけではないが、それからしばらく走りつづけたように思う。
4日に「講座・戦後教育実践書を読む」の第1回をもった。予想通りではあったが、参加者は少なく、主催者としては惨敗の思い。(今は仕方ないのだ)と思いながらもやはり悔しい。その思いを、佐野真一の「遠い『山びこ』」のあとがきの一部に語ってもらう。
30年後、山元中学校に赴任してきた渋谷正は、「山びこ学校」を使って輪読会を開いた事があったが、生徒は本に出てくる方言がまったくわからないと言いだした。テレビの普及は、30年前村内でやり取りされていた言葉を子どもたちの間から奪っていた。渋谷は作文を書かせてみたが、見るべき成果は得られなかった。親たちの生活が見えてこないから、問題意識も生まれてこないのだろう。
渋谷の前にいる子どもたちの関心は、もっぱら将来の生活に向けられていた。「山びこ学校」の子どもたちの関心が、現在ただいまの生活をどうすべきかという一点に絞られていた。「山びこ学校」の子どもたちは貧しくはあったが、自分たちのまわりには打開すべき現実が確固としてあった。30年後の子どもたちのまわりに貧しさはなかったが、自分が主人公になれる現実もまたなかった。
「山びこ学校」の子どもたちにとって、村の現実を学ぶことはすなわち世界を学ぶことだった。30年後の子どもたちの学習は、偏差値序列にしたがって想定されるあやふやな未来像に向けての、せめてもの預託行為だった。そこに「山びこ学校」の子どもたちの幸福もあれば、30年後の子どもたちの不幸でもあった。
今、この渋谷正の山元からさらに30年を重ねた。佐野は「そこに『山びこ学校』の子どもたちの幸福もあれば、30年後の子どもたちの不幸でもあった」と言っているが、現在、何人の教師が、親が、この佐野の言葉を素直にうけとめるだろうか・・・。
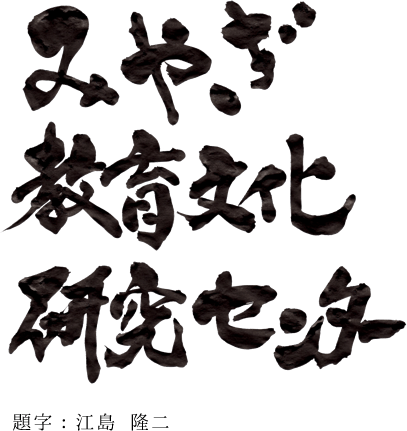
 トラック島にいると言われていた父は何日待っても音沙汰なく、突然翌年、霞ヶ浦の病院にいるとの連絡があり、母が迎えに行き、仙台の大学病院で手術、病名はアメーバー赤痢。これは母から聞いたもので、父は病気のことも含めて戦地のことは何一つ言わなかった。しばらく仕事に就けない間、休職教師の父と2人で紙巻きタバコつくりをして闇で売り生活の足しにした。これが唯一の父との思い出と言っていいかもしれない。
トラック島にいると言われていた父は何日待っても音沙汰なく、突然翌年、霞ヶ浦の病院にいるとの連絡があり、母が迎えに行き、仙台の大学病院で手術、病名はアメーバー赤痢。これは母から聞いたもので、父は病気のことも含めて戦地のことは何一つ言わなかった。しばらく仕事に就けない間、休職教師の父と2人で紙巻きタバコつくりをして闇で売り生活の足しにした。これが唯一の父との思い出と言っていいかもしれない。