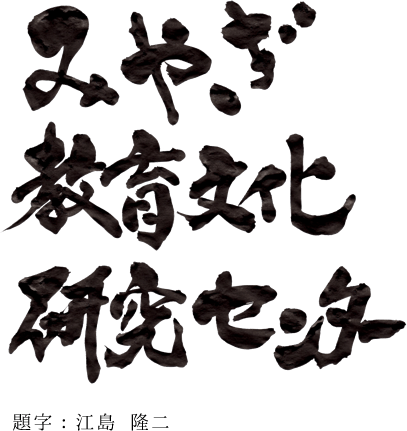2024年03月06日
今年の1月、耳を疑うようなニュースが飛び込んできました。奈良教育大学附属小学校において、教育課程の実施等に関し法令違反を含む不適切な事案がある。それは学習指導要領に示されている内容の実施不足(授業時数・履修年次・評価の実施不足等)、教科書の未使用等である。そこで学校の教員を大量に他の学校へ出向させるというものです。
具体的には毛筆指導、図工、道徳、外国語、君が代の指導などが不十分であることや、職員会議の決定権が強く校長の権限を制約していることなどに疑問を感じたと、校長は説明していました。 もう少し具体的に言えば、習字の時間がなかったというけど、実際は筆ペンを使ったのがいけないということらしい。いろいろな地域からバス通学する子どもたちの荷物を減らそうという配慮だったというのが事実。図工の授業も教科書を使用していないというけど、保護者からは「描くデッサンから始まり、絵の具の使い方、パレットの使い方、そんな基礎は教科書には書かれてない。全校絵画展をみて作品の素晴らしさを観て欲しい」と先生達を支持する声も届いています。 そもそも大学の付属学校の校長は、私の知るかぎりでは、その大学の教授が勤めているはずが、奈良教育大学の今回の校長は、4月に教育委員会から派遣されてきたそうです。奈良教育大学付属小の実践をつぶそうという意図がみえみえです。 我が身を振り返ってみれば、書写の時間数、図工の指導、道徳の内容、君が代の指導、教科書の未使用、プリント教材の作成など、どれもが私の実践内容と重なるものばかりです。
今、全国の多くの研究者や教師たちが、奈良教育大学附属小学校の教師たちへの処分とも言える出向命令に異議を唱えて、署名運動が急速に広がっているのは当然です。
そこで40年ほど前、学習指導要領の法的拘束力について考えたメモノートがあることを思い出し、改めてワープロで打ち込み直しをしました。
現在、教育基本法も改悪され、最新の学校教育法も読んでいないので、多少、現状に沿わないことがあるとは思いますが、あえて紹介します。
「学習指導要領の法的拘束力について」
学習指導要領が初めて作成されたのは1957年。当時、文部省はこの学習指導要領について、次のような説明を行っています。
『この書は、学習の指導について述べるのが目的であるが、これまでの教師用書のように、1つの動かすことのできない道をきめて、それを示そうとするような目的でつくられたものではない。新しく児童の要求と社会の要求に応じて生まれた教育課程をどんなふうに生かして行くかを教師自身が自分で研究していく手引きとして書かれたものである』(学習指導要領一般論・試案、序論 昭和22年度文部省)
ここにで分かるとおり、学習指導要領には、戦前に用いられた「教師用書」のような「法的拘束力」はまったくないこと、また「拘束力」をもたせることは、子どもの教育にとってどんなに有害であるかを、文部省自身が説明していたのです。
それではいつから学習指導要領の法的拘束力がいわれるようになったのか。それは1958年の第3回目の学習指導要領のときから、試案の2文字が外され、告示の形になりました。そして文部省は、制度的には学校教育法施行規則が、文部省の一存でつくれるのをいいことにして、国民に計ることなく、その25条を一方的に次のように変えてしまいました。
それまでは、「小学校の教育課程については学習指導要領の基準による」となっていた条文を、「小学校の教育課程については、(中略)教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする」と中略以下の文を付け加えたのです。中学・高校についても同じです。そして、それまでの「試案」の2文字を消して、官報での「告示」欄で公示しました。
文部省はさらには次のように言い出しました。<学習指導要領には法的拘束力があります。なぜなら、学校教育法施行規則に「小・中・高」の教育課程は、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する学習指導要領によるものとする」となっているからです。また、政府が法令の公布などを国民に知らせるための官報でも、「告示」されています。だから学習指導要領には「法的拘束力」があるのです>と。
しかし、このような言い分は通りません。なぜなら学校教育法施行規則に書かれていることが「法的拘束力」をもつためには、まずその内容が学校教育法にきちんと書かれていなければならないはずです。ところが学校教育法には、そのようなことはどこにも書かれていません。法律に書かれていないものに「法的拘束力」が生ずるわけがありません。
では学校教育法には一体どんなことが書かれているかをみてみます。学校教育法には、「教科に関する事項は……監督庁が、これを定める」(第20条)、また監督庁は「当分の間、これを文部省とする」(第106条)と書かれています。
つまり学校教育法には、文部省は「小(中・高も同じ)学校の教科に関する事項」を「定める」ことができるとだけ書いてあり、学校教育法が、教科に関して文部省にあると認めている権限はこれだけです。従って学校教育法では、文部省が「教育課程の基準として」の学習指導要領をつくることはできないようになっています。
この「教科に関する事項」とは、子どもの学習権と国民の教育水準の確保のために、どうしても全国的に共通でなければならない、国語や算数などの教科名、標準授業時数、高校の卒業単位などのことを指す言葉だからです。つまり、教育の内容や方法まで文部省が決めていいなどとは、どこにも書かれていません。それは教育基本法第10条で教育行政が教育内容にまで立ち入ることをきびしく禁止していることからしても当然のことです。
しかし文部省はどうしても教育内容を権力的に統制したいがために、とんでもないすりかえを行いました。それが「教科」と「教育課程」のすりかえです。つまり学校教育法でいう「教科」とは「教育課程」と同じだという強弁です。
もともと「教育課程」とは「教科」と「教科外」をふくむ教育活動の全体を指す言葉です。従って、「教科」よりはるかに広い範囲の内容を含んでいます。それなのに文部省は勝手に同じものだと言っておいて、<学校教育法には「教科に関する事項は文部省が決めることができる」と書いてある。ところがこの「教科に関する事項」とは「教育課程」と同じ意味である。だから文部省は、教育課程の基準として「学習指導要領」をつくることができる>とごり押ししたのです。二重三重のペテンとしか言えません。